2日目に入る前に、長沢地区の基本的な情報を説明します。
長沢は、伊予桜井から西条方面へ向かう最初の踏切辺りから、「道の駅 今治湯ノ浦温泉」を含む2km以上ある縦長のエリアで、7つの集落で構成されています。
長沢の地理的特徴と組織運営
7つの集落はそれぞれ名前があり、「道の駅 今治湯ノ浦温泉」から順番に以下のようになっています。
- 「元瀬(がんぜ・がんじょ)」
- 「上の谷(かみのたに)」
- 「久保の谷(くぼのたに)」
- 「岡の谷(おかのたに)」
- 「下の谷(しものたに)」
- 「三の谷(さんのたに)」
そして、国道196号線を挟んだ反対側の「猿子(さるご)」の、計7つの集落で長沢は構成されています。
これらの地区は協議会によって統合されており、自治会も存在しますが、長沢の組織運営は主に協議会が担当しています。
長沢の協議会は、7つの集落からそれぞれ7人の協議員が選出され、地区全体を総括する地域の代表者「惣代(そうだい)」、補佐として「副惣代」、さらに「宮惣代(神社惣代)の計10人が定期的に長沢集会所に集まり、協議をしながら地域の運営をおこなっています。
長沢は名前に「谷」とつく地区が多いことからも分かるように、谷間の地形を持っており、この地形のため隣の谷の状況が分かりにくく、情報が谷間に留まりがちです。
協議会はこの問題を解決する手段としても機能しています。
今回の山林火災では、出火元と見られる「元瀬」の奥川の山林から「三の谷」まで順番に燃えていき、長沢だけではなく、高麗池方面、そして伊予桜井駅の周辺から海方向の養護学校がある山までもが被災しました。
この火の流れは強風によって非常に早く、予測困難な状態ではありましたが、惣代を筆頭とした協議会のシステムの中で、できる限りの情報は地元住民の間で迅速に共有されていました。
田舎の情報はネットよりも速いといわれることがありますが、今回の火災ではその良い面が顕著に表れ、住民の同士の安否確認や避難の呼びかけなどが効果的に行われていたと思います。
さらに、今回の記事の最後にその理由を説明しますが、「火の見張り」も大きな役割を果たしました。
では、2日目に入ります。
深夜の停電と本格的な避難準備
2025年3月24日(月曜日)、深夜3時に家の電気が突然切れました。
窓の外をみれば信号も街灯もすべて消え、周囲は真っ暗闇に包まれました。
外は煙と焦げ臭い匂いが辺りに漂っていました。そんな煙が漂う真っ暗闇の中で、オレンジ色の山火事の明かりだけが見えていました。
特に、朝倉方向から見える赤い光は、笠松山(2008年の山火事)が再び燃えているのではないかとの不安を掻き立てました。
一方、停電したものの、ソーラー街灯や手持ちのライト、懐中電灯やキャンプ用ライト、発電機に投光器もあったので、すぐには深刻な問題にはなりませんでした。
後から調べると、これは計画的な送電停止だったようです。
3月23日に愛媛県今治市で発生した山林火災に関し、消火活動における公衆感電等の
二次災害を防止するため、同市の一部地域において送電停止(保安停止)を実施しており
ます。愛媛県今治市の山林火災に伴う保安確保のための送電停止(保安停止)について/四国電力送配電株式会社.2024年3月24日
この時、とある出来事が一気に心配になりました。
「同居している90歳のおばあさんの夜間のトイレはどうすれば」
おばあさんはその時は眠っていて、遠くの山頂の鉄塔に電力会社の作業員が真っ暗な中、ヘッドライトを頼りに鉄塔に登っていく様子を窓から見守っていました。
この時に自分の中で避難が現実味を帯びました。
午前4時になると電力が回復し、山の上の真っ暗な鉄塔に登る作業員の姿は、本当にかっこよくみえました。
ほっと一息つきながら、朝が明けたらすぐにおばあさんを親戚の家へ避難させることを決めました。
同時に、自分たちもいつでも避難できるように準備を始めました。
ほとんど寝ずに2日目の朝
ほとんど眠っていないまま迎えた早朝5時頃、少しずつ明るくなり始めた中で、SNSを通じて朝倉方向に火の手が進んでいることを知りました。
地元の人からは、「道の駅 今治湯ノ浦温泉」から西条方面にある孫兵衛作地区でも被害が甚大であると聞かされました。
後のテレビの報道で、住民がバケツリレーで必死に火を消している様子が映されていました。
そして孫兵衛作では、消防団の成り手不足で消防団がなかったということも知りました。
この自分たちで小さな火を消すという行動は、火の広がりと共に他の地区で見られました。
私も安全な場所から小さな火や、燻っていた煙などに水をかけて、少しでもなんとかしようとしました。
196号線の封鎖解除と迫りくる火の手
6時になり、外が完全に明るくなると、窓からテレビ局の人たちが地域を回って取材しているのが見えました。
また、道路は静まり返っており、車の通行はほとんどありませんでした。
昨晩から続いている196号線の通行止めがまだ解除されておらず、タオル美術館側の道だけが今治から西条へのルートとして使われていました。
朝の7時頃には196号線の通行止めが解除されたようで、徐々に車通りも増えていきました。
通勤時間には、特に大きな混乱もなく、落ち着いているようさえ見えました。
しかし、確実に火の手は迫っていました。
煙に包まれた地元と神社焼失の危機
この日は、日中の気温が20度を超え、地表の乾燥が進んでいました。
夜から続く強風が火の勢いを増す一因となり、午前11時頃には、笠松山の方向から吹き付ける強風によって、長沢地区の半分が煙で覆われました。
その影響で、太陽はまるでオレンジ色に染まったかのように見えました。
この時、再び「須賀神社・長沢」が危険な状態にある聞きました。
もはや緩衝地帯と考えていた工事中の高速道路が機能していないほど、火の勢いは増していたのです。
この時も、消防の方々の賢明な活動により、神社の焼失はなんとか防がれました。
しかし、この日から数日にわたる強風は火の勢いと広範囲にわたる飛び火を引き起こし、その制御はほぼ不可能となっていきます。

ヘリが空から消火活動を開始
前日(3月23日)に自衛隊のヘリコプターを要請していたため、いつ消火活動が始まるのかと待ちわびていました。
そして13時50分頃、自衛隊ヘリが消火活動をしているのを目撃しました。
さらに、応援に来てくれた徳島の消防防災ヘリも確認しました。
愛媛県のヘリは前日から既に消火作業をしていましたが、日没までしか飛べないため、前日は火災発生時が夕方近くであり、加えて現場が遠かったため、私はその様子を見ることができませんでした。
ヘリは「三嶋神社・旦」や「特別養護老人ホーム 唐子荘」近くの高麗池から水を汲み上げ、上空からピンポイントで水を投下していました。
この消火活動は非常に効果的で、火の勢いは大幅に抑えられ、一部の場所では火が完全に消えたように見えました。

2つの防衛ラインを同時に超える
午後2時、これまで燃えていた山から一つ手前の山で突如火柱が上がりました。
これは、一つ目の重要な防衛ラインと考えていた工事中の高速道路を完全に越えたことを意味しました。
同時に、裏側から山林沿いに燃え広がると想定していた、2つ目の防衛ライン(トンネル)も突破されたことになりました。
まさかこんなにすぐに超えるとは…。
強風と火が合わさった時の飛び火の恐怖を感じながらも、自分が住む場所からはまだ距離があったため、まだ直接的な脅威を感じませんでした。
地元を捨てる覚悟
しかし、我々が置かれた緊迫した被災状況に変化はありません。
避けようのない火の脅威がいずれ自分たちの住む地まで迫ることは避けられず、谷の中、山のふもとに位置する私たちの集落は、やがて180度炎に囲まれる運命にありました。
この現実に直面し、私たちはある種の重大な決断を迫られました。それは、もし必要ならば地元を捨てるという覚悟です。
この決断は、単に物理的な場所を離れるという意味を超え、これまでの生活や記憶、そしてコミュニティの一部を放棄することを含みます。
火災が迫るにつれて、その現実はより鮮明になり、心の準備をせざるを得ませんでした。
そして、いざこの状況になった時には「ついに来たか…」という気持ちでいられました。
もちろん、完全に平常心を保つことはできませんでしたが、地元の人々は驚くほど冷静でした。パニックに陥って慌てて逃げる人は一人もいませんでした。
それは、まさに覚悟だったと思います。
一方で、逃げることを拒む人もいました。そうした人々を強引にでも安全な場所へ連れて行くべきだったのか、今でもその答えを模索しています。
祖母が先に避難
同じ頃、一緒に住んでいた90歳の祖母が、安全な別の地区に住む親戚の家へと避難していきました。そして、私もいつでも避難できるように準備を始めました。
火災拡大の瞬間をドローンが記録
15時頃、強風が火の広がりを加速させる中、状況確認のためのドローンが空を飛んでいました。風に煽られる火は、一層の勢いで周囲の林木を飲み込んでいきました。
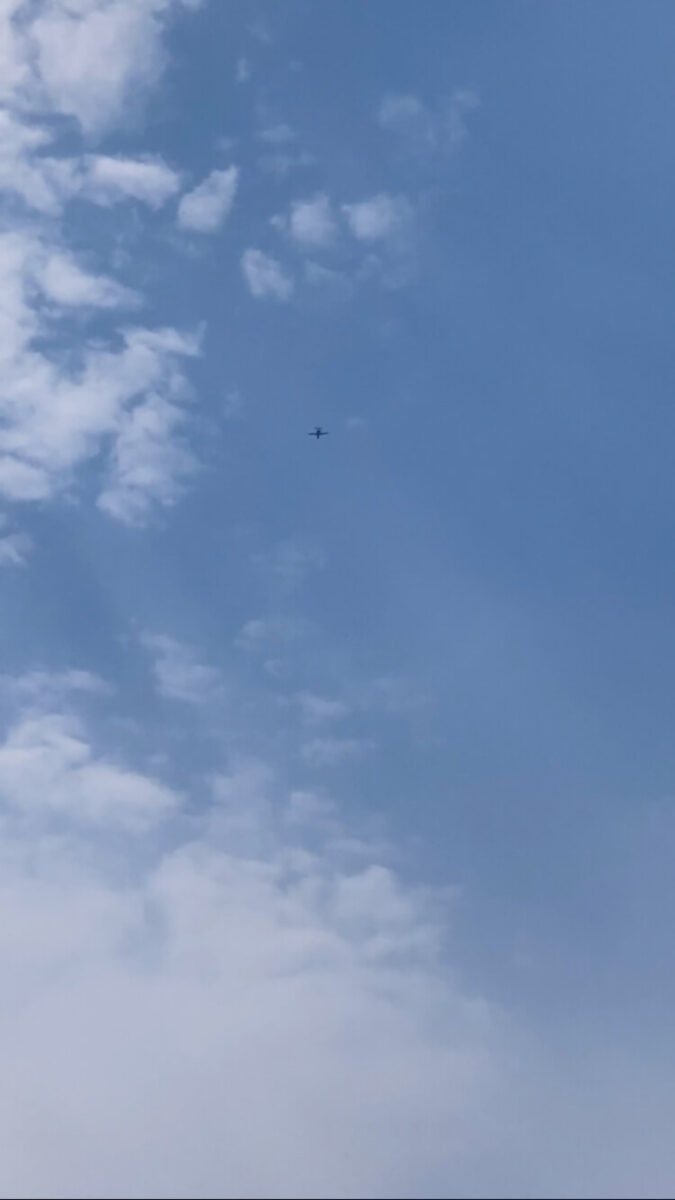
朝倉側の様子と後ろからも迫る炎
16時15分頃、朝倉地区での用事を済ませた後、火災の反対側の状況を確認するために地元を離れました。
この時、緑ヶ丘団地に炎が迫っているのを目視で確認し、長沢地区全体も横だけでなく後ろからも炎に包まれつつある状況が見て取れました。
16時40分頃には長沢に戻り、その様子を撮影した動画を地元の人々に見せました。
地上からは山林火災の全体像を掴むことが難しく、特に反対側の状況については報道ヘリのライブ映像に頼るしかありませんでした。
この動画からも、反対側の長沢地区が煙につつまれていたのがよくわかります。
17時の緊迫と混乱
17時になると、地元では有名な美しい陽光桜と桃の花が咲いている場所のすぐ裏まで火が迫りました。
ものすごいスピードで進行する火災に、なすすべもありませんでした。さらに、日没が迫りヘリからの消火活動も止まってしまうため、いつどうなってもおかしくない状況にいました。
ライフラインの情報についての混乱
この頃には友人から、水道水があまりでなくなった連絡が入りました。
まさか火災の影響で断水?なぜ?と相談していましたが、この時は結局わからず…。
後になって、消火の影響で水がでにくくなっていたことを知りました。
電気・水道・そして交通にしろ、告知こそされていましたが、差し迫った危機が目の前にあったため、これらの情報については、後から知ることが多かった気がします。
山を挟んで両サイドに集結する消防車
17時30分になる頃には、朝倉の緑ヶ丘団地が危険という情報が入りました。
16時30分頃「緑ヶ丘団地がそろそろヤバい」と皆に伝えてから、ほんの少ししか時間が経っていません。
……あまりにも火の広がりが早過ぎる。
この時、長沢は西条方面、そして朝倉方面の二つの方向から同時に火が迫り、周囲は完全に茶色い煙に包まれ、いつどこで民家が燃え始めてもおかしくない状況でした。
そして、緑ヶ丘団地もそうですが、長沢にも住宅を死守するため消防車が集結し始め、一つの山を両サイドから挟む形になりました。
例えるなら、水の壁とでもいうのでしょうか?消防の人々は民家を死守するため、限られた消防力の中で水の壁を作りながら、火の広がりと共につねに移動していました。
逆に言えば、消防車が多く集まっている場所は、最悪の状況が間近に迫っているということでもありました。
避難しても必ず明日には現地に戻る
この時に、すでに避難の準備を整えていた私は睡眠を別の場所でとる、つまり避難することに決めました。
これは、火の広がりが前日に比べて明らかに速くなり、さらに朝倉側から音もなく迫る火を気にしながら、眠りにつくことは考えられなかったためです。
私たちの地域の人々は、すでに避難について話し合っており、多くが親戚や知人の家など、さまざまな場所で避難をすることを決めていました。
しかし、避難所となっている公民館には避難せず、翌日の朝には高齢者を除くほどんどの人が被災地となる地元に戻る予定でした。
理由はさまざまですが、人手不足の中で火の粉が瞬く間に大きく燃え広がる様子を目の前で目撃し、小さな火でも誰かが消火してくれるのをただ待っているわけにはいかず、自分で水を撒いたりしなければならなかったのも大きな理由の一つでした。
離れた場所での平穏
被災地となった地元から少し離れると、そこには普通の日常が広がっており、頓田川(とんだがわ)を超えると、まったくの他人事のように感じられるほどでした。
そのため、パニック買いもなく、必要な物資はどこでも容易に手に入れることができました。
実際、避難指示が発令されて、封鎖された地域の中にあっても、一定の距離をとることで比較的安全に行動することができていました。
常に逃げる準備だけはしっかりと整え、つねに屋外にいるという条件付きではありますが、私たちは基本的な日常活動を継続することができていました。
しかし……その中で眠ることだけは命に直結する危険な行為でした。
19時30分に必要なものを全て詰め込んだ車に乗り込み、避難を開始しました。
避難が完了したのは20時頃で、それとほぼ同時に緑ヶ丘団地地区に避難指示が出されのを覚えています。
避難前には、一度火が収まったと思われた場所から再び火柱が上がり、それはまるでジブリ映画『風の谷のナウシカ』に描かれる火の七日間のように思えました。
明日の朝にはうちは全部燃えてるかもな……。
ゾンビのように蘇る炎の恐怖
この日、今治市消防本部から13隊63人、今治市消防団から15台100人が参加し、合計163人が地上から消火活動をおこなってくださいました。
また、西条市の消防の方々もこの日から消火活動を始めました。
さらに、徳島からの応援を含む2機の消防防災ヘリコプター、自衛隊ヘリコプター3機が空から散水しましたが、それでも火の勢いは衰えず、人手はまだ不足しており、燃え広がる火を抑えこむことは出来ませんでした。
前回の記事と重複しますが、ヘリからの消火はかなりの効果がありましたが、夜には活動できないため、一度は消えたようにみえた場所からゾンビのように炎が立ち上がってきました。
消防のホースは、山間部まではとどかないため、火が消火ができる範囲内にくるまでは基本的にはどうすることもできませんでした。
火のないところに煙は立たないと言いますが、煙が見えないところからいきなり火柱があがるケースも何度もありました。
変わりゆく風向き、強風、そして地形の複雑が火災の拡大を加速させ、消火活動をさらに困難にしていたのです。
もはや終わらせるには雨しかありませんでした。しかし、雨の予定は3日後の3月37日(木曜日)。
それまで持つのかな……。
危険な夜も地元に残り続けていた人々とその理由
このような状況の中で、危険な夜になったとしても避難せずに、現場には地元の人が常駐していました。
「なんで?」「さっさと避難しろ」
と思うかもしれません。
しかし、これは今回の災害の特殊性だと感じています。
どうしても地元に詳しく、土地勘のある人が現場にはいなければいけなかったのです。
昔は普通に通れていた道だとしても、過疎化によって管理ができなくなり、今では人が進むことができなくなっていました。
消火をする際、それらの状況がわからないことは致命的でした。
特に、応援に来てくださった、愛媛中、広島や香川から来てくださった消防隊員のたちには、これらの地域の特性を正確に伝えることが極めて重要でした。
そのためにも、現場には地元の人が必要だったのです。
もちろん安全を配慮しての距離は大事でしたが…。
「トリアージと119」見張りの大切さ
もう一つ、避難せずに残り続けていた重要な理由があります。
それが火の見張りです。
この頃には災害の規模が大きくなっており、消防の方々も人手が不足しているため、少しばかりの煙ぐらいでは、119をしても来ていただけるのはかなり後になっていました。
「人が居住する建物、住宅だけは絶対に守り切る」
このトリアージがおこなわれていたのです。
実際に消防の方から「“火が見えたら”すぐに連絡してください」と言われていました。
しかし、煙が火に変わるのは一瞬の出来事で、その連絡が少しでも遅れれば致命的な結果に繋がります。
そのため、必ず誰かが「火の見張り」をする必要がありました。
燃え盛る山々に囲まれ、どの方向から火が迫るか予測できない中、私たちは一日中、煙と火を警戒し、地元を常に見守っていたのです。
朝から夜になるまで、見通しのいい場所で煙を見続け、その日はそこから火が上らないこともありました。
しかし、不安は消えません。
気になって、夜中に何度も起き、以前煙が見えた場所を確認していました。
「煙だけかな?」と思っていた翌日の昼下がり、気温が上昇し草木が乾燥する中、突然、火柱が上がりました。
こうなるとすぐに119をして、すぐにでも消火して頂かないとさらに別のエリアに燃え広がります。
しかし、現実的にはその時に119をしても間に合わず、消防の方々が到着するころには別の場所へ火が進行した後になってしまいます。
なので、煙の色が白から灰色へ、灰色から黒に変わるなど、変化が起きた時にありとあらゆる角度から火を探し、火が見えたと確信した瞬間に119をしていました。
それでもなお、人手不足の中ですぐには来ていただけませんでした。
そんな状況だったのです。
警察までも人手不足なのか、覆面パトカーまでもが動員されており、日にちが進むにつれ、スーツを着た刑事系の方々も交通整理に参加していました。
消火が間に合わない状況では、諦めるか、安全に配慮しながら自分で消火するしか方法はありません。
距離をとりながら自分たちで火を消していた、消そうとしていたという話をいくつか聞いています。
特に、自分たちの地区は農業をする人が多かったため、消毒をしたり水を汲み上げる機械が手元にありました。
それを初期消火のために使うことがありました。
実際に自分もしました。
「自分の身は自分で守る」
これは防災の一番重要な理念の一つですが、必ずしもこのようなリスクをとれということではありません。
この行動は、まったくもって他人に推奨できることではありません。
しかし、何もしなければさらに燃え広がっていたのは事実です。
今回の山林火災は恐怖というよりも、地域全体で何度も蘇る火「ゾンビ火災」との戦いといったイメージでした。
……もちろん消防士の方々には遠く及びませんが。
夜に避難をしなかった人がいたのは、以上のような理由です。
もちろん、夜に残っていた人々も、安全な場所に車を移して、いつでも逃げられるように準備していました。
夜になっても、地元の誰かが何かをしており、火の発生場所を警戒し続けていました。
そのため、私も早く戻って何かをしなければという思いが強く残っていたのです。
安全な場所には避難しましたが、結局心配のためほとんど眠れませんでした。
このような状況の中で、翌日には火はさらに勢いを増して燃え広がることとなりました。
